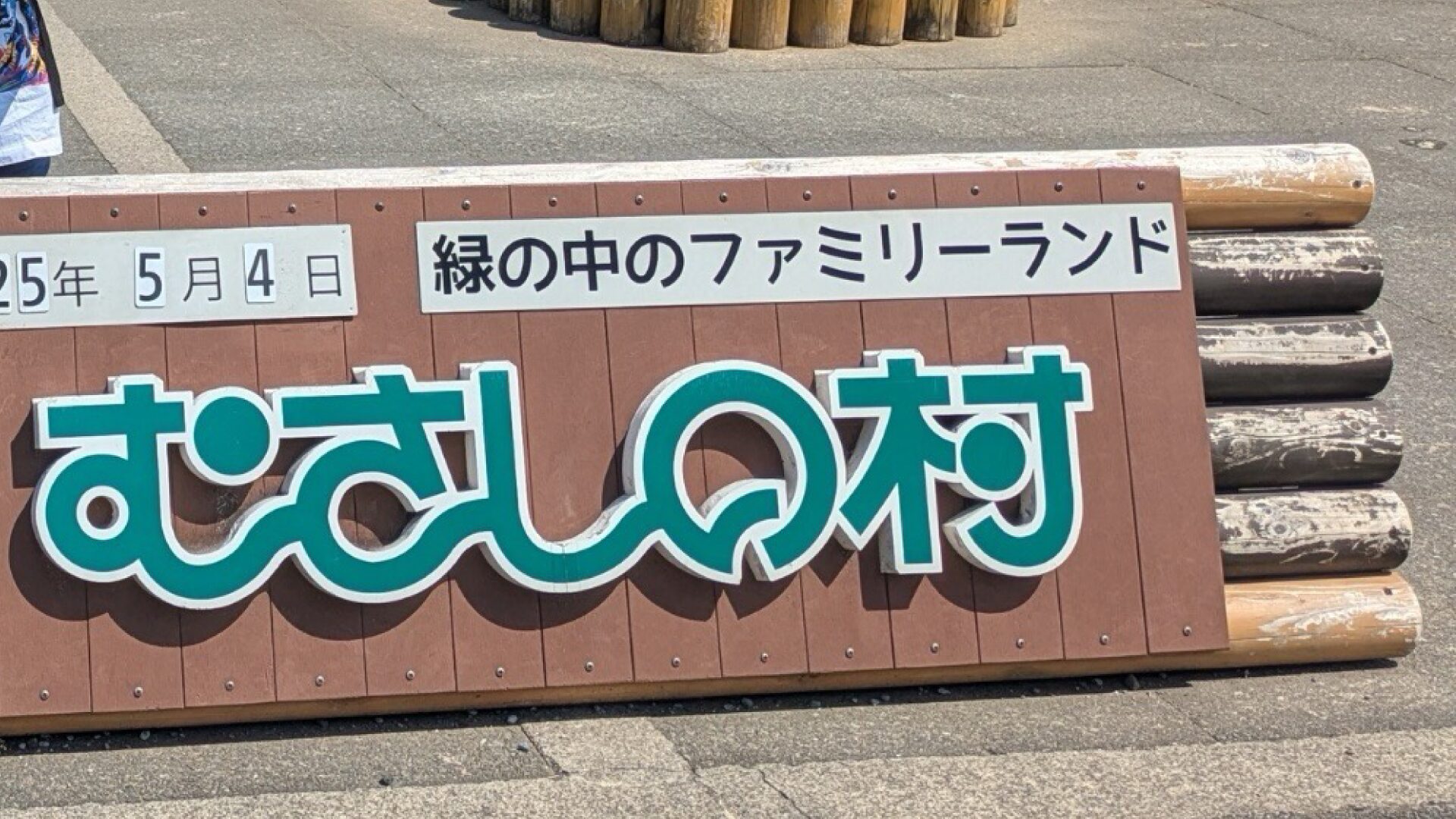本ページはプロモーションを含みます。
最近は幼稚園や保育園の頃、人によっては入園前からゲームやYouTubeに親しみ、幼い頃からデジタル機器を使うのが当たり前な時代でもあります。小学校に入学すれば、タブレット学習やパソコン学習が待っていますし、お勉強もデジタル機器で行う時代。親世代が子どもの頃とは状況が違います。私は幼い頃からデジタル機器に触れさせる事は悪いとは思いません。ただ、ゲームやYouTubeに依存し過ぎてしまったり、ゲームがないと癇癪を起こして止められない!となると話が変わって来ます。また発達途上の子どもの視力への影響も、子どもの健康の事ですから、気になって当然かと思います。しかし、そんなデジタルネイティブな子ども達とデジタル機器を切り離すのは簡単な事ではありません。無理に禁止するとその欲求不満が別のところで爆発するかもしれませんし、別に「デジタル機器=悪」ではないと私は思います。大切なのは、「デジタル機器と上手にお付き合いすること」ではないでしょうか。特に「使用時間」は健康面への影響としても重要な点かと思います。我が家にも5歳の子どもがいて、ゲームやYouTubeの使用時間のルールを設けて工夫をしています。今回は我が家の場合のデジタル機器のゲームやYouTubeの時間のルール作りのコツをお伝えします。それぞれのご家庭のお子さん達に合わせてカスタマイズして、活用して頂けたら幸いです。
【何歳からデジタル機器に触れさせた?】
1歳半頃に子ども専用タブレット購入
先述したように我が家は、デジタル機器=悪という考えは持っていないので、上の子が1歳半頃に子ども専用のタブレットを購入しました。このスタート年齢は賛否両論あるかもしれません。しかし、何をしてもグズってどうしようもない時のYouTubeが、現実問題として、とても有難い存在だった!という事もあります。実際育児をしてみて、YouTubeで子ども向けのチャンネルの童謡などを流したら、子どもが泣き止んで助かった!という経験のある方も多いのではないでしょうか?ただ、スマホだと画面が小さくて見づらいという難点がありました。なので、我が家では子ども専用のタブレットを購入しました。
大切なのはルール
すると、いろんな事の吸収が早い年齢だったからか?1年も経つ頃には、1人でタブレットを起動して、好きなYouTubeを見たり、幼児学習アプリで遊んだりするようになっていました。なので、タブレットの操作は2歳にして問題なくできていました。これぞデジタルネイティブ!という感じですが、ただただ好き放題見させてしまうと先述のような健康への懸念も出てきますよね。なので、我が家ではいくつかのデジタル機器におけるルールを幼い頃から当たり前のように教えてきました。5歳半になる今もきちんとルールを守れています。
【我が家のゲーム・YouTube時間ルール その①】1回15分ルール
我が家では「1回15分ルール」を設けています。これは、いわゆる趣味や娯楽としてゲーム・YouTubeなどをNintendo Switchやタブレットで使う1回の時間の長さを15分にするルールです。え?15分?!短くない?!と思う方もいるかもしれませんが、これは1回の時間であって、その日の日程に合わせて、回数は2〜4回の中で調節して設定しています。具体的には、平日の夕方まで幼稚園に行っている日は1日の内2回、つまり15分×2回で30分自由に使ってよいよ!と伝えています。また、平日のお昼過ぎまで、もしくは半日保育の日は1日の内3回、つまり45分に設定しています。そして、何も予定のない休日はマックスの4回、つまり1時間に設定しています。お出かけの予定があったりする休日はその時間に合わせて臨機応変に設定しています。その日使ってよい時間を朝本人から聞いてくるので、「2回だよ」とか「3回だよ」と伝えてあげています。15分使ったら、途中でも一度止めて、数分でも休憩を挟んでから、続きをするようにもしています。
1回15分ルールで健康面への心配も軽減
時間を明確に設定することで、延々と使い続けてしまうという健康面での心配を防げます。また、1回何分と設定して、今日は何回やってよいよ!と伝える事で、その日の予定に合わせて臨機応変に時間設定する事ができます。また、休憩を挟む事で、ゲームやYouTubeに集中していた意識が現実世界に戻ってきて、リフレッシュにもなりますし、ずっと画面を見続けることを避け、健康面もケアします。
【我が家のゲーム・YouTube時間ルール その②】タイマーを使う
15分ルールはご理解いただけたと思いますが、実際どうやるの?時計もまだ読めない年齢なのだけど…という事もあるかもしれません。我が家では、タブレットに入れてあるタイマーのアプリを使って、時間になったら、自動的にその画面が表示されるようにしています。また、「リリリリリリリリ!」というアラーム音で周囲も15分使ったんだなと解ります。なので、例えば、夕食の時間が近い時にアラームが鳴れば、「もうすぐお夕食だから、次の1回はお夕食が終わってからやろうね」と声かけする事ができます。また、もし残り7分の時に夕食の準備が整った場合でも、「もうお夕食の準備が整ったから、アラームを1回止めて、残りの7分はお夕食後にしようね。お夕食後も楽しみだね。」と声かけをすることで、アラームを止めて、夕食後に続きができます。
時間管理能力向上などのメリットも
このようにアラームを活用する事で、臨機応変に物事をスケジュールしていくという力が身に付き、時間管理能力の向上にもなるかな?と思っています。また、今上の子は5歳半ですが、調度時計が少しずつ読めるようになってきている時期なので、この年頃になれば、時計の勉強にも繋がり、一石二鳥なところもあります。
【我が家のゲーム・YouTube時間ルール その③】お手伝いや勉強で稼ぐ!
お手伝いや勉強で稼ぐ!我が家の場合の具体例
基本的には、先述したようにその日の予定によって1回15分のゲーム・YouTube時間が何回できるかは決まっていますが、お手伝いや勉強を規定量した場合は、その分が追加される仕組みにしています。具体的には、お手伝いを5回したら、1回分追加!という具合です。勉強に関しては、まだ幼稚園児ですが、通信教育をやっていて、そのワーク15ページで1回分追加!としています。
我が家はZ会のワークを使用
我が家ではZ会幼児コースの通信教育教材を活用しています。ワークも「かんがえるちからワーク」と「ぺあゼット」の2種類があります。年中・年長は提出課題やデジタル教材もあるので、バラエティに富んでおり、やる気の継続にも繋がるよい教材だと思います。気になる方は是非下記より資料請求してみてください。質の高い教材を実感できるはずです。
行動の目的性は?
しかし、これでは純粋な気持ちで「勉強すること」や「お手伝いすること」を目的に行動できていないではないか!ゲーム・YouTubeが目的になっている…それはどうなのか?という点で、これも賛否両論あるやり方かな?とは思います。しかし、純粋に勉強やらお手伝いを目的にいつもできる子って少ないと思うのです。自分が気が向いた時にやるよ…となって、どんどんワークがたまっていってしまったり、こちらから声をかけないとお手伝いしない…という事もあると思うのです。もちろん勉強やお手伝いを目的に行動できれば、それは素晴らしいことです。ただ、我が家は昔はなかなかそれが難しい状況でした。
やらなければならない事を頑張る力の向上
しかし、勉強やお手伝いは、ゲーム・YouTube時間という自分のやりたい事をする時間を増やす手段!と設定した途端に、今まで1ヶ月あってもなかなか終わらなかったワークが1週間で終わり、お手伝いも積極的に自分から「何かお手伝いある?」と聞いてくるようになりました。例え目的がゲーム・YouTube時間を稼ぐ事であったとしても、他の事もその為なら頑張れる!という力がつきました。仕事もそうですが、もちろん仕事自体に目的性を持って仕事をする事も大切ですが、家族のためだったり、お金を貯めてほしいものを買うために仕事を頑張れる!という事もあると思うのです。これはその事自体のモチベーションに関わらずやらなければならない事を頑張る力に繋がるかなと思います。
【我が家のゲーム・YouTube時間ルール その④】好きなだけできる使い方も
我が家では、デジタル機器の使用を全て制限してはいません。常識的な限度はありますが、好きなだけ使って良い使い方も2つ決めています。
祖父母とのビデオ通話
1つ目は祖父母とのビデオ通話です。ゲーム・YouTubeとは違い、ビデオ通話は相互的なものですし、コミュニケーションの1つになります。祖父母の都合やこちらの食事の時間に問題なければ、好きなだけ通話して良いとしています。祖父母も喜んでくれていますし、子どもも楽しんでいます。下の子のお世話で親が対応できないタイミングなどでも、祖父母との通話が活躍する事もあります。
お勉強としての使用
2つ目は学習アプリや通信教育のタブレット学習などのお勉強としての使用です。これは、お勉強であって、遊びであるゲーム・YouTube時間とは区別しています。お勉強としてのデジタル機器の使用は好きなだけやってよいとしていたからか?上の子は4歳の時点でひらがなもカタカナも読み書きが全てできていました。また、5歳の現在は小学生向けの「ほねほねザウルス」や「ざんねんないきもの事典」や「最強王図鑑」の本をスラスラ読めるようになっています。
ゲーム・YouTube時間を味方に付けて、子どもの成長のサポートに
ゲーム・YouTube時間も工夫次第で、様々なメリットに繋がります。
- 物事に取り組む時に時間を決めて取り組むという時間管理能力の向上
- 集中と休憩のメリハリを付ける力の向上
- 時計の勉強のきっかけ
- その事のモチベーションに関わらずやらなければならない事を頑張る力の向上
などなど…ゲーム・YouTubeと子どもというとネガティブなデメリットが頭に浮かぶ人も多いかもしれませんが、工夫次第で、子どもの成長機会に繋がるかもしれません。今の時代、デジタル機器と子どもの生活は、なかなか切り離せるものでもありません。ポジティブな側面も視野に入れて、デジタル機器と上手にお付き合いができるとよいですね。